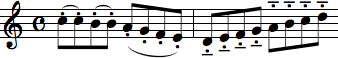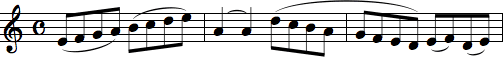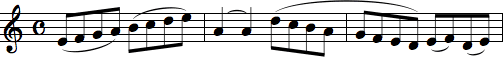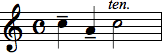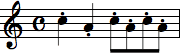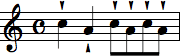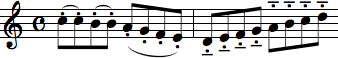ある音から次の音へ、どのように移ってゆくかを、アーティキュレーションといいます。
スラー
- 音をなるべくつなげて演奏することを「レガート」(legato)といいます。レガートを表す記号を、「スラー」といいます。
- タイ同様、弧線で表されますが、同音の「たま」と「たま」とを結んでいればタイ、そうでなければレガートです。
- 弧線の左端がスラーの起点で、弧線の右端がスラーの終点です。全体でひとまとまりとなるようにするのですが、細かくいうと、終点以外の音を、それぞれ次の音につなげるようにします。
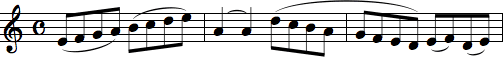
- 楽器によっては、スラーが奏法を示すことがあります。擦弦楽器(ヴァイオリンなど)では、弓を返さずに同一方向に弾き続けることを示します。また、管楽器の場合には、なるべくタンギングをしないで演奏することを示します。
- 声楽の場合には、歌詞のひとつの音節が続くことを示すことに使われます。楽譜によっては、8分音符以下では連桁がその役のスラーのかわりを示すことがあります。
テヌート
- 音を、示された音価の中で、なるべく長く引き延ばして演奏することを、「テヌート」(tenuto, ten.)といいます。弦楽器や管楽器では、その音の間、一定の強さを保つように演奏します。
- 記号で書くこともあれば、文字で書き示すこともあります。
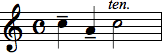
- テヌートは、その音をしっかりと他の音と分けて演奏することも示します。従って、実際の演奏では、示された音価よりわずかに短く切り上げて、次の音との間に間を空けることも、しばしばあります。
スタッカート
- 音を短く切って演奏することを「スタッカート」(staccato, stacc.)といいます。音の長さは音価よりも短くなり、その分、次の音との間に空白が生じます。
- 通常のスタッカートは点で示されます。1/2の長さといわれますが、実際にはそれよりも短くなることが普通でしょう。
- スタッカートが続くときは、文字で(staccato, stacc.のように)書かれることもあります。
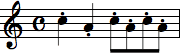
スタッカーティシモ
- 非常に短く切るスタッカートを「スタッカーティシモ」といい、くさび形の記号で示します。1/4の長さといわれますが、実際にはそれよりも短くなることが普通でしょう。
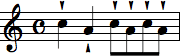
メゾスタッカート
- スタッカートよりも長く切る、または柔らかく切るスタッカートをメゾスタッカートといいます。
- メゾスタッカートは、スラーやテヌートとスタッカートの組み合わせで示されます。スラーを使うメゾスタッカートは、擦弦楽器の楽譜では、スラーのように弓を返さずに演奏することを示します。