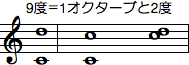オクターブ以内の音程と、オクターブを超える音程
- オクターブを越える音程を、「複音程」と呼びます。これに対し、オクターブ以内の音程は「単音程」と言います。
- 8度以下の音程は一般に単音程ですが、増8度と重増8度は、複音程の性質を持っています。
- また重増7度は、ピアノではオクターブを超えますが、単音程です。
複音程の呼び方
- 複音程では、オクターブ単位で音程を縮めて考えます。
- 例えば、次の音程は、

単音程と同じように数えると9度です。
- これは、1オクターブ縮めると2度になりますので、「1オクターブと2度」(または単に「オクターブと2度」)とも呼びます。
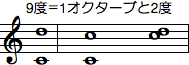
- この2度は長2度です。ですから、「1オクターブと長2度」(「オクターブと長2度」)と呼びます。
- これは「長9度」と呼ぶこともあります。このように、「オクターブを」を使う言い方でも使わない言い方でも、数字の前にそえる半音を表す言葉は同じになります。
- この2つの言い方を比較してみます。
- 9度=(1)オクターブと2度
- 10度=(1)オクターブと3度
- 11度=(1)オクターブと4度
- 12度=(1)オクターブと5度
- 13度=(1)オクターブと6度
- 14度=(1)オクターブと7度
- 15度=1オクターブと8度、2オクターブ(と1度)
- 16度=2オクターブと2度
- 17度=2オクターブと3度
......
- 21度=2オクターブと7度
- 22度=2オクターブと8度、3オクターブ(と1度)
- 23度=3オクターブと2度
このように
nオクターブとm度=7n+m
が成り立つことがわかります。
- 複音程の全音階的・半音階的、また、協和・不協和の分類は、相当する短音程と同じです。たとえばオクターブと長3度は、全音階的音程で、不完全協和音程です。
複音程の転回
- 複音程を転回するには、単音程に直してから転回します。たとえば、長9度(オクターブと長2度)の転回音程は、長2度の転回音程と同じで、短7度です。
- 増8度、重増8度も同じです。増8度(オクターブと増1度)の転回音程は増1度の転回音程と同じで、減8度です。
楽典の本によっては、複音程の転回音程は、「オクターブ縮めた音程」としているものがあります。これに従えば、長9度の転回音程は、長2度ですが、これでは実用的な意味がありません。
問題
関連サイト