付点音符
- 次のように、音符の「たま」の右に点を添えたものを「付点音符」といい、元の長さの1.5倍の長さを表します。それぞれ元の音符の名前に従って、「付点○分音符」等々のように呼びます。たとえば、「付点4分音符」は4分音符の1.5倍の長さを表します。
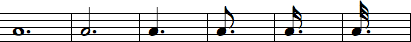
- 音符の「たま」が五線の線上にあるとき、点は、上にずらすのが普通です。

ただし、2パートで「ぼう」の方向を上下に分けているとき、下のパートは付点を下にずらすことがあります。
- 元来は、点自体が、元の音符の0.5倍の長さを表しました。ですから、次のような書き方が行われたことがあります。(なお、この場合は、「たま」が線上にある場合、付点も線上に書かれます。)
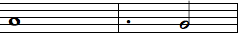
これは、次の意味です。
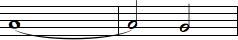
付点休符
- 休符にも、付点があります。付点休符といい、「付点○分休符」等々のように呼びます。
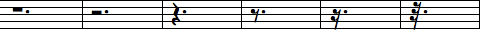
クラシック音楽の楽譜では、付点音符はなるべく使わない傾向にあります。たとえば、付点4分休符は、4分休符と8分休符を並べて書いて代用します。
付点のリズム
- 付点音符は、元の音符の半分の長さ(付点音符の3分の1の長さ)の音符とペアで使われるのが普通です。たとえば、

のように。これは合わせて2分音符

の長さになります。元の音符の倍の長さです。
また、同じように

のように使われます。これは合わせて4分音符

の長さになります。そして、たとえば前者ならば2分音符を、後者ならば4分音符を、それぞれ3:1に分割したリズムです。これを俗に「付点のリズム」と呼びます。
ところが、実際には、曲によっては、「付点のリズム」で書かれたリズムを、3:1ではなく、2:1、5:1等々に分割すべきことがあります。これは、その曲の書かれた時代、作品の様式等によって、判断することになります。一般にロマン派中期以降のクラシック音楽では、正確に3:1と捉えるのが一般的です。詳しくは連符の組み合わせのページをお読みください。
- 付点音符が休符と組み合わされることもありますが、

このような書き方を嫌い、

のように書く作曲家もいます(フランスの作曲家など)。
- いわゆる「付点のリズム」の逆のリズムでも、付点音符は使われます。俗に「逆付点」と呼びます。

- 逆付点の場合には、次のように付点休符を使うことはありません。

付点音符の特性
- 付点音符は、元の長さの1.5倍の長さがあります。これは、0.5倍の長さの3倍です。すなわち、付点音符を3等分すると、ひとつが元の長さの2分の1の長さの音符で書き表すことができるということになります。
 ⇒
⇒ 


複付点音符
- 付点音符の仲間に、複付点音符があります。付点を2つ並べて書きます。これは、元の音符の1.75倍(1+½+¼)の長さを持ちます。

- 複付点音符は、元の音符の4分の1の長さの音符と組み合わせられて、全体で元の音符の倍の長さを持ちます。

 ⇒
⇒ 
- 複付点音符は、読みにくいという理由で、あまり使われません。たとえば、次のようにタイと付点音符を使って書き分けられることが行われます。

または

問題
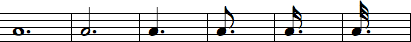

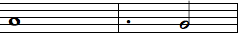
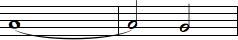
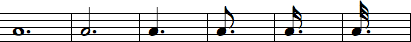

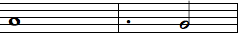
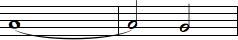
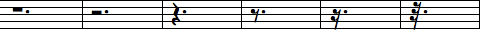








 ⇒
⇒ 




 ⇒
⇒ 

