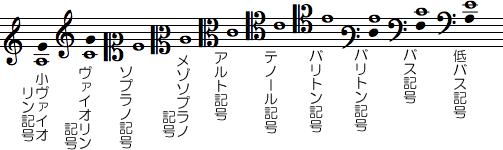音の高さを楽譜で表すには、五線と音部記号を用います。
五線
- 音の高さを表すには、まず五線を用います。五線は、等間隔で平行な5本の線です。
- 五線は、相対的な音の高さを表します。
- 五線の上の方が音が高く、下の方が音が低くなります。

- 五線には、線と、線と線の間に音符の「たま」を置くことができます。線が5本、間が4つ、その他に線の上下に置くことができますから、置き位置は11あります。「たま」の位置で音の高さが決まります。

- それ以上に高い、または低い音を書く場合には、線を臨時に加えます。これを加線と言います。

- 隣同士の置き位置は、音の高さが隣り合っていることを意味します。隣り合っているとは、ピアノの白鍵の隣同士のことです。または、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ....」の隣同士です。

- それぞれの置き位置には、名前が付いています。

- 線には下から番号が振られています。
- 線と線の間にも下から「第○間(かん)」のように番号が振られています。
- 加線には五線に近い方から「上(かみ)第○線」「下(しも)第○線」のように名前が付いています。
- 五線の上下に接したところは「上第1間」「下第1間」のように呼びます。「上第1間」と「下第1間」を示すだけのためには、加線は必要ありません。
- 加線と加線の間には、五線に近い方から「上(下)第2間」「上(下)第3間」のように数えます。
音部記号
- 五線は、音の相対的な位置を表すだけです。これだけでは音符が何の音を表しているのかはわかりません。そこで、絶対的な音を表すために、音部記号を用います。音部記号には、「ト音記号」「ヘ音記号」「ハ音記号」があります。
- 音部記号でもっとも用いられるのは「ト音記号」です。ト音記号は、その記号の丸くなっている中心が「ト」(G、ソ)の音であることを表します。「ト」にもいろいろありますが、中央ハ音(ピアノでちょうど真ん中に付いている鍵穴に最も近い「ハ」(C、ド)の音)のすぐ上の「ト」
を表します。「高音部記号」とも言います。
 (この図の横線は、五線の内の1本です。わざわざこの線を書くわけではありません。以下の記号でも同じです。)
(この図の横線は、五線の内の1本です。わざわざこの線を書くわけではありません。以下の記号でも同じです。)
- 「ト音記号」の次によく用いられるのは「ヘ音記号」です。ヘ音記号は、2つの点の中心が「ヘ」(F、ファ)の音であることを表します。ヘ音の中でも、中央ハ音のすぐ下の「ヘ」
を表します。「低音部記号」とも言います。

- ヘ音記号は
 のように書かれることもあります。
のように書かれることもあります。
- 用いられる機会は少なくなりますが、「ハ音記号」というものもあります。ハ音記号は、2つの点の中心が「ハ」(C、ド)の音
であることを表します。ハ音の中でも、中央ハ音を表します。「中音部記号」とも言います。

- ハ音記号は
 のように書かれることもあります。特に手書きのときには、この記号の書き方をすることが多いようです。
のように書かれることもあります。特に手書きのときには、この記号の書き方をすることが多いようです。
- 音部記号は、五線の任意の位置に置かれ、基準となる音を示します。
音部記号は、音部記号が書かれたところよりも右に効力を発しますから、通常五線の最初(左端)には音部記号が置かれます。
五線は音部記号と音符との相対的な関係を示しますから、音部記号が五線のどの高さに置かれるかによって、五線が示す音の高さも変わってきます。
ト音記号は異なる2つの位置に置かれ、ハ音記号は5つ、ヘ音記号は3つの位置に置かれて、それぞれに名前が付いています。
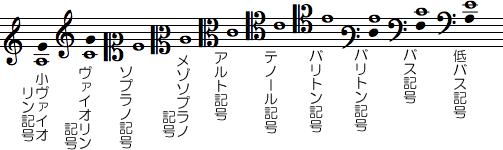
- 上の楽譜で、白音符は中央ハ音を、黒音符はト音記号とヘ音記号でその基準となるそれぞれト、ヘの音を示します。
- 現代の楽譜で通常使われるト音記号は「ヴァイオリン記号」、ヘ音記号は「バス記号」です。
- アルト記号はヴィオラの楽譜に常用されます。
- テノール記号はオーケストラのテノールトロンボーンの楽譜に常用されます。また、ファゴット、チェロの高音域を表すのによく使われます。コントラバスの高音域を表すのに使われることもあります。
- バリトン記号はハ音記号を使う場合とヘ音記号を使う場合がありますが、いずれも五線と音との関係は同じです。
- 音部記号は、途中で変わることがあります。通常、小節の変わり目で音部記号が変わる場合には小節線の左に書きます。段の変わり目の場合、前の段の最後に予告の記号を書きます。小節の途中で音部記号が変わる場合もあります。

譜表
- 音部記号で音の高さが規定された五線(及び類似のもの)を、譜表と言います。
- ヴァイオリン記号(ト音記号・高音部記号)の付けられた譜表を高音部譜表、バス記号(ヘ音記号・低音部記号)の付された譜表を低音部譜表と言います。
- ピアノのように、広い音域をひとりで演奏するために、高音部譜表と低音部譜表をかっこでくくった譜表を大譜表と呼びます。(ただし、実際には、ピアノの楽譜では、上の段を主として右手用、下の段を主として左手用とし、それぞれ必要に応じて途中から音部記号を変化させることが行われます。)

オクターブ記号
- 音符を、一時的にオクターブ上げたり下げたりする記号があります。次の楽譜の音符は、すべて同じ高さです。

- オクターブ上げるときは五線の上に8vaと書き、点線で範囲を示します。範囲の終わりは、縦に点線を書きます。8vaのかわりに8とだけ書いたり、8va altaと書くこともあります。
- オクターブ下げるときは五線の下に8vaと書き、点線で範囲を示すのが普通です。8vaのかわりに8とだけ書いたり、8va bassaと書いたりする場合もあります。
- まれに、2オクターブ上下する記号を使うことがあります。15maまたは15と書きます。
- 音符の上、または下に、8とだけ書き、点線がない場合には、その音とオクターブ上(下)の2つの音を同時に(和音で)演奏することを示します。
- 音部記号の上、または下に8と書いてある場合には、その音部記号の有効範囲全体をオクターブ上げて(下げて)演奏します。ソプラノリコーダーではよく、ト音記号の上に8と書いた楽譜を使います。また、声楽のテノールの場合には、ト音記号の下に8と書いた楽譜を使うことがあります。いずれにしても、楽器(声域)でわかるので、8の数字を省略することがあります。
問題










 (この図の横線は、五線の内の1本です。わざわざこの線を書くわけではありません。以下の記号でも同じです。)
(この図の横線は、五線の内の1本です。わざわざこの線を書くわけではありません。以下の記号でも同じです。)

 のように書かれることもあります。
のように書かれることもあります。

 のように書かれることもあります。特に手書きのときには、この記号の書き方をすることが多いようです。
のように書かれることもあります。特に手書きのときには、この記号の書き方をすることが多いようです。