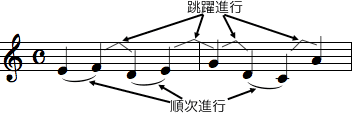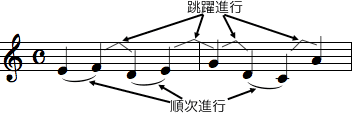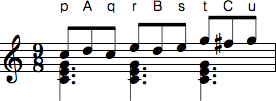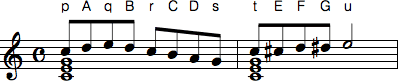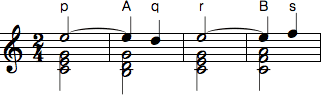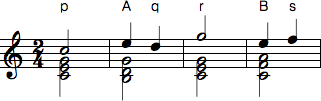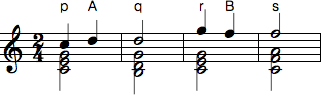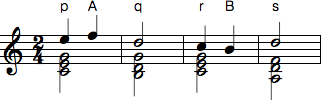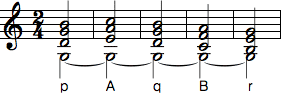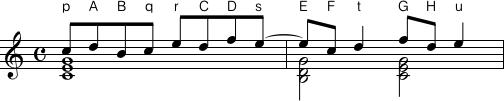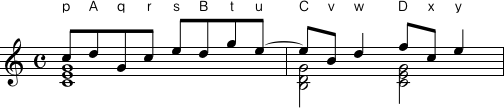西洋音楽では、旋律などは、和音の構成音を中心に作られますが、和音の構成音だけで旋律が作られることは滅多にありません。和音の構成音以外の音がどのように現れるかを考えます。
非和声音とは
- 非和声音とは、その時に鳴っている和音の構成音以外の音が、旋律などに鳴らされることをいいます。
- 「和声」とは、「和音と各パートの音のつながり」の意味です。「非和声音」といいますが、「和声的でない」という意味ではありません。本来は「非・和音・音」とでもいうべきでしょうが、このように言い習わされてます。
- 別の呼び名で「和声外音」というのもあります。同じものを表しますが、これもこれらの音が和声から外れているなどというわけではありません。これも「和音外音」とでも呼ぶべきでしょう。
- 和声学の本によっては、「転位音」と呼んでいます。和音構成音から一時的に隣接する音に変化した音、という考えからです。
- 非和声音は、一般に、前後の和音構成音とのつながりを基準に、7つに分類されますが、実際にはこれらの中間的な非和声音や、どれにも分類できないものがあります。
順次進行と跳躍進行
このページでよく使われる用語です。
- ある音から次の音に移行することを、音楽理論では一般に「進行」と呼びます。
- 2度で進行することを「順次進行」と呼びます。
- 3度以上の進行を「跳躍進行」と呼びます。
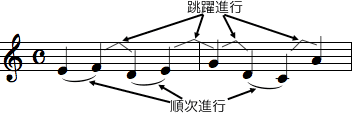
- 音が緊張した状態から弛緩することを、「解決」と呼びます。非和声音は緊張した状態なので、非和声音が進行して非和声音でなくなる(和音構成音になる)のも「解決」のひとつです。
刺繍音(補助音)
- ある和音構成音(譜例p、r、t)から、非和声音(譜例A、B、C)に順次進行して動き、元の音(譜例q、s、u)に戻る、この非和声音を「刺繍音」または「補助音」と呼びます。
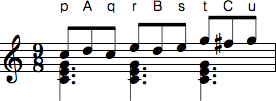
- 下に進行して上に戻る刺繍音は、その進行が本来長2度となるとき、刺繍音が半音上げられて短2度進行となることがあります(譜例C)。
経過音
- ある和音構成音から、別の和音構成音へ(譜例p→q、q→r、r→s、t→u)、順次進行でつなぐときに、間にはいる非和声音(譜例A、B、C、D、E、F、G)を「経過音」と呼びます。
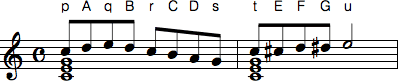
- 2つの和音構成音が3度のときには経過音は1つですが、4度のときには2つになります(譜例C、D)。
- また、経過音が半音階的にはいることもあります(譜例E、F、G)。
掛留音
- 和音の変わるときに、前の和音の和音構成音(譜例p、r)が引き延ばされ、新しい和音で非和声音(譜例A、B)となって、新しい和音の構成音(譜例q、s)に2度進行して解決するとき、この非和声音を掛留音といいます。2度下がる形(譜例A)がより伝統的な形です。なお、譜例p、rのような音を、「掛留音の予備」と呼びます。
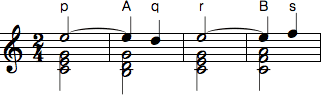
掛留音は、解決が引き延ばされて、次の和音で解決することがあります。次の譜例で、Aは、通常の掛留音です。BはAと同様ですが、その和音の間に解決せず、次の和音で解決(譜例s)しています。
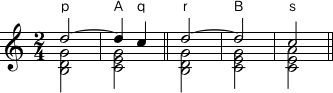
倚音
- 先行音(譜例p、r)から、和音の変わり目に跳躍進行して非和声音(譜例A、B)となり、順次進行して和音構成音(譜例q、s)に解決する非和声音を、倚音といいます。
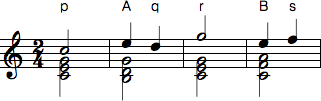
- 倚音も、解決が引き延ばされて、次の和音で解決することがあります。下の譜例Bは、下の譜例A同様ですが、解決が引き延ばされて次の和音で解決(譜例s)しています。
- 倚音は譜例Aのように和音の変わり目に起こるのが原則ですが、譜例Cのように同じ和音の中で和音構成音(譜例t)から跳躍して倚音にはいるものもあります。通常の倚音と同様に順次進行して和音構成音(譜例s)に解決します。
- 以上の2つが組み合わさって、すなわち和音構成音から同じ和音の中で跳躍して倚音(譜例D)に入り、解決が引き延ばされて次の和音で解決(譜例w)するものがあります。これを「後部倚音」と呼ぶことがあります。
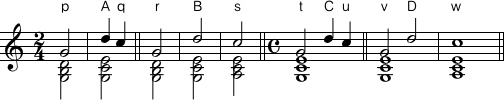
先取音
- 和音の変わる直前に、次の和音の構成音を先取りして非和声音(譜例A、B)となり、新しい和音に入ったときに同じ音を打ち直す(譜例q、s)、この非和声音を、先取音といいます。通常、先行音(譜例p、r)から順次進行して先取音になります。
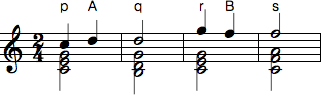
逸音
- 和音の変わる直前に、和音構成音(譜例p、r)から順次進行して非和声音(譜例A、B)となり、和音が変わると同時に跳躍進行して新しい和音の構成音(譜例q、s)に解決する非和声音を、逸音といいます。
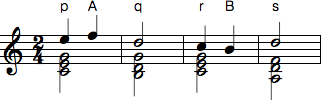
保続音
- 和音が変化しても、同じ音が鳴り続けることによって、非和声音(譜例A、B)となるものを、「保続音」といいます。「オルガン音」「オルガンポイント」「オルゲルプンクト」とも呼ばれます。和声の本によっては、変化する和音の方を非和声音(たとえばAの部分なら上3パートが刺繍和音、Bなら上3パートが経過和音)と捉えるものがあります。保続音は多く、最低音パート(バス)に現れます。
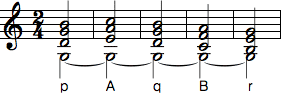
二重非和声音
- 非和声音が和音構成音に解決する前に他の非和声音を経由することを、二重非和声音と呼ぶことがあります。二重非和声音の2音は、互いに、もう一つの非和声音がなければ普通の非和声音と同じです。
- 下の譜例で、Aはqに解決する前に非和声音Bを経由しています。もしBがなければ、Aは、和音構成音pからqに解決する普通の上方刺繍音です。一方、もしAがなければ、Bは、和音構成音pからqに解決する普通の下方刺繍音です。このように上方刺繍音と下方刺繍音がいったん和音構成音に戻らずに連続して現れるのを、二重刺繍音と呼ぶことがあります。CDも、上下が逆なだけで、同じように二重刺繍音です。
- 非和声音Eは和音構成音tに解決する前に非和声音Fを経由しています。もしFがなければ、Eは、和音構成音sに予備された普通の掛留音です。このような掛留音を二重掛留音と呼ぶことがあります。
- 非和声音Gは和音構成音uに解決する前に非和声音Hを経由しています。もしHがなければ、Gは、普通の倚音です。このような掛留音を二重倚音と呼ぶことがあります。
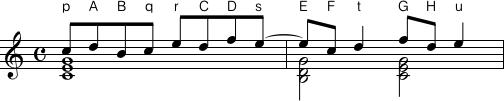
非和声音と分散和音
- 非和声音の解決は、他の和音構成音が分散和音のように挟まることによって引き延ばされることもあります。下の譜例では刺繍音(譜例A、B)、掛留音(譜例C)、倚音(譜例D)が、それぞれ他の和音構成音によって引き延ばされています。
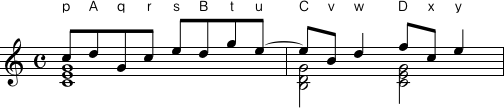
問題