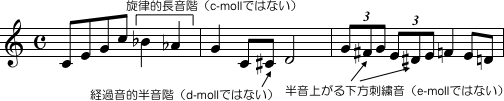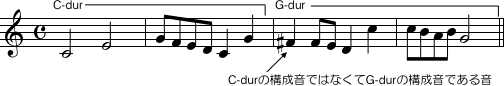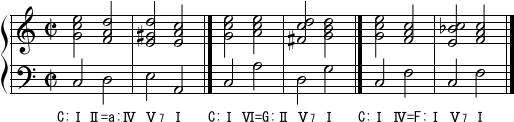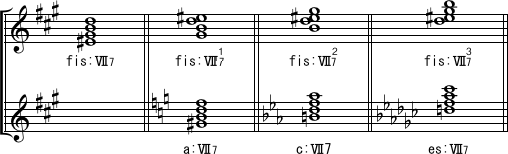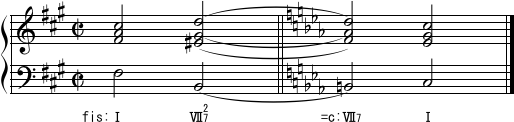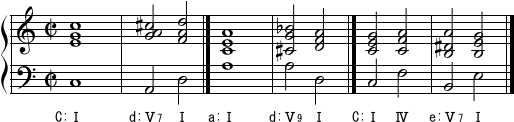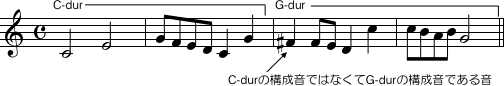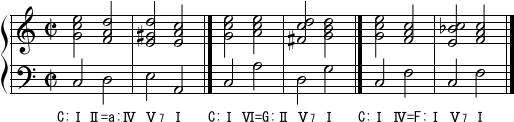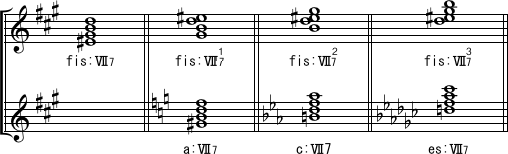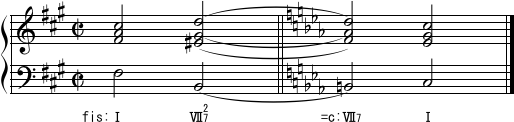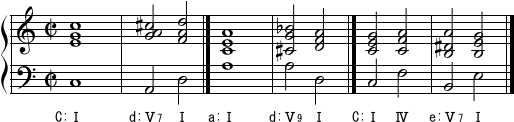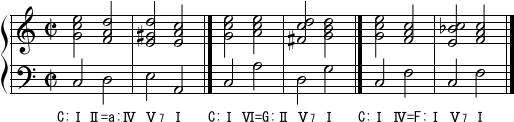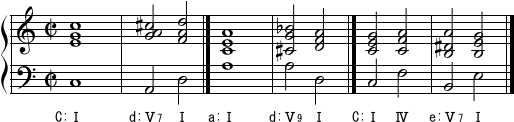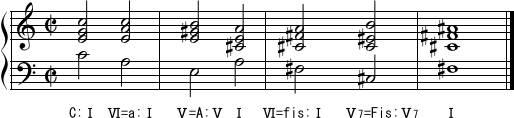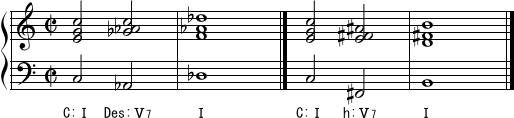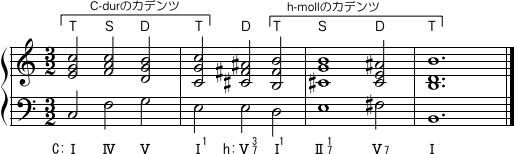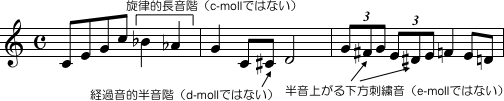曲の途中で調が変わることを転調といいます。
転調のプロセス
- 転調においては、多くの場合、前の調の構成音に含まれなくて新しい調の構成音に含まれている音(新しい調の特徴音)が聞かれることによって、新しい調が知覚されます。次の例では、C-durになくてG-durにあるfis音が特徴音となって、移調を知覚します。
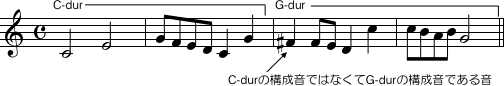
- 転調では、通常、和音の変化が重要な働きをします。
- 転調を和音の変化で分類すると、前後の調に共通する和音の読み替えによるものと、新しい調の和音にいきなり入るものに分類できます。
- 共通和音の読み替えによる転調の例を示します。最初の例ではC-durから平行短調のa-mollへ転調しています。先行調C-DurのIIを後続調a-mollのIVと読み替えています。また次の例ではC-durのVIを属調G-durのIIに、最後の例ではC-durのIVを下属調F-durのIに読み替えています。
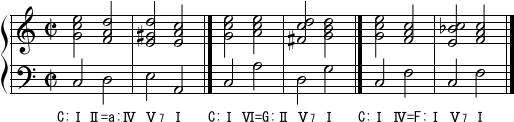
- 短調のVII7は減七の和音です。減七の和音は、3つの短3度で構成されています。ところで、第7音と(その上の)根音との間隔も(減7度の転回音程の)増2度の異名同音程の短3度ですから、実質、4つの短3度を積み上げて(オクターブ上の)もとの音に戻る和音です。それゆえ、減七の和音の第1転回形は短3度上の減七の和音の基本形と同じ響きであり、第2転回形は減5度上の基本形と、第3転回形は減7度上の基本形と同じ響きになります。従って、ひとつの減七の和音で、4つの根音の減七の和音、すなわち4つの短調のVII7に聞かせることができるのです。次の譜例はfis-mollのVII7がa-moll、c-moll、es-mollのVII7に読み替えられることを示しています。上下で同じ響きになります。
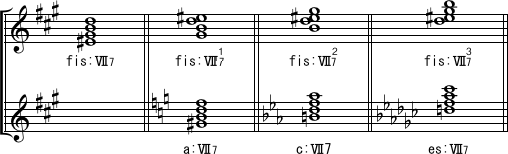
これを利用した転調も行われます。次の例では、fis-mollのVII7の第2転回形をc-mollのVII7に読み替えています。
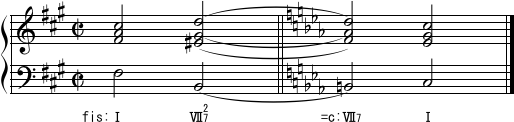
- 次に共通和音の読み替えによらない転調の例を示します。前の調の任意の和音から、新しい調のV7(またはその類似の和音である、V9、VII、VII7)に直接入るだけで、新しい調に移行することができます。
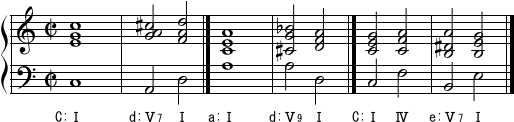
2つの調の関係による転調の分類
- 転調で、古くから数多く行われているのは、近親調への転調です。
(再掲)
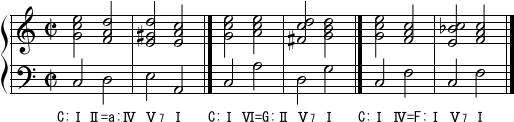
(再掲)
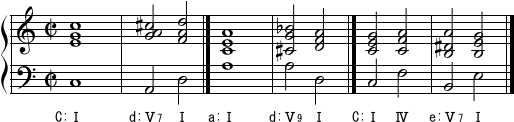
- 近親調以外の調(遠隔調)への転調では、転調を連続して行うことがあります。同主調への転調(調号3つの増減)を介せば、調号の大きく異なる調へも簡単に移動できます。次の例では、C-durから平行調のa-mollさらに同主調のA-dur、平行調fis-moll、同主調Fis-durと移行することで、遠隔調へ転調しています。
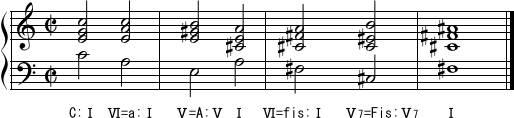
- 遠隔調の転調は、より簡単には、新しい調のV7を用いた転調が行われます。
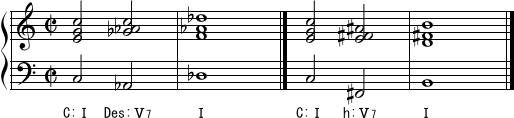
調の確保
- 調の変化がしっかりと認識されるためには、転調の前後の調がそれぞれしっかりと認識されなくてはなりません。調を調としてしっかりと認識させることを調の確保、調の確立といいます。
- 調の確保では、カデンツが中心となります。T-S-D-Tのカデンツは確実に調を確保します。
- 最初に述べたように、ある調で演奏されているうちに、その調の構成音でない音が出てきたら、転調かも知れません。しかし、明らかに転調であると言うためには、前後の調の確保がされていることを確認する必要があります。次の例では、C-durでカデンツが鳴らされた後、h-mollに転調してから、h-mollのカデンツが鳴らされています。
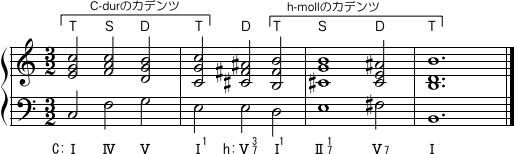
- 調の構成音の中には、短調では和声的短音階のほかに、旋律的短音階や自然短音階、長調でも自然長音階の他に和声的長音階や旋律的長音階を含めて考える必要があります。また、ある調の中で、一時的にその調の構成音でない音を使うことはよくあります。経過音的な半音階や、半音上がる下方刺繍音は、その例です。これらの場合は、それだけでは転調とは呼べません。