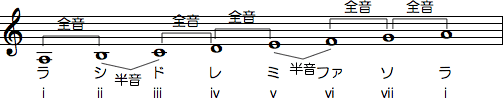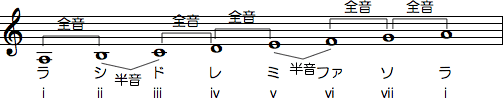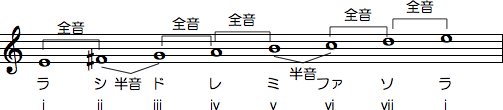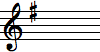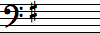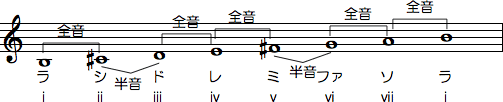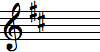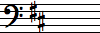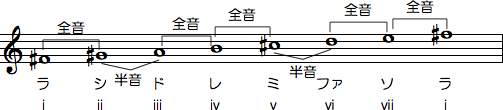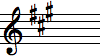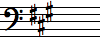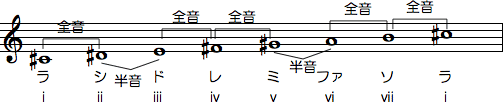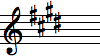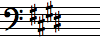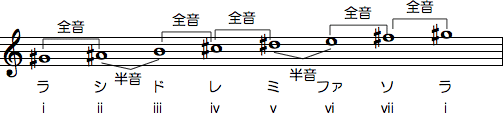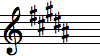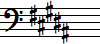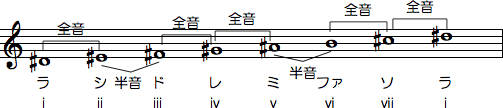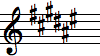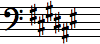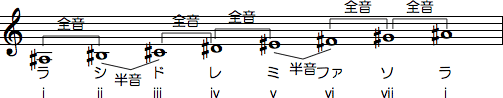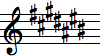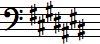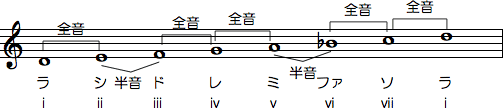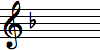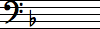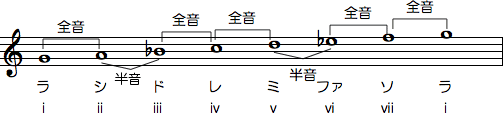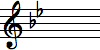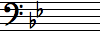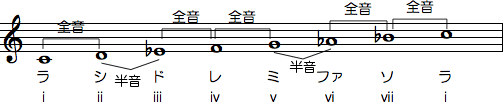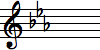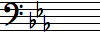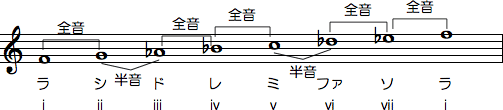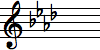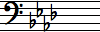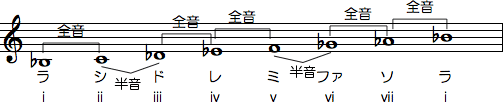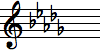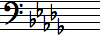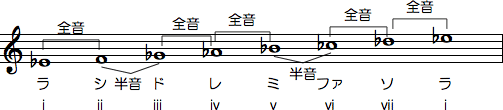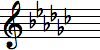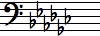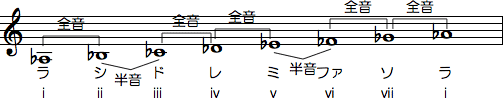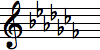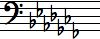短調
短音階に基づく音楽を短調と言います。英語ではMinor、ドイツ語ではMoll(モル・ただし日本では普通「モール」と読む)と言います。
イ短調
ホ短調
ロ短調
嬰ヘ短調
嬰ハ短調
嬰ト短調
嬰ニ短調
嬰イ短調
嬰種短調
- これまで挙げた、ホ短調から嬰イ短調までの長調を、♯(嬰記号)が付く短調という意味で、「嬰種短調」と言います。一般には「♯系の短調」という言い方もします。
- 嬰種短調は、短3度上の主音を持つ長調と同じ調号を持ちます。
- 嬰種短調の調号を書くには、主音を短3度上げて、その長調の調号を書きます。
- 調号から嬰種短調の主音を知るには、その調号の長調の主音を短3度下げます。または、3度下げて、調号を見れば、主音に♯が付くかどうかがわかります。
ニ短調
ト短調
ハ短調
ヘ短調
変ロ短調
変ホ短調
変イ短調
変種短調
- これまで挙げた、ホ短調から変イ短調までの長調を、♭(変記号)が付く短調という意味で、「変種短調」と言います。一般には「♭系の短調」という言い方もします。
- 変種短調は、嬰種短調同様、短3度上の主音を持つ長調と同じ調号を持ちます。
- 変種短調の調号を書くには、主音を短3度上げて、その長調の調号を書きます。
- 調号から変種短調の主音を知るには、その調号の長調の主音を短3度下げます。または、3度下げて、調号を見れば、主音に♭が付くかどうかがわかります。
問題
- 調号の種類と数を答えましょう。
- ハ短調
答え [表示]答え [隠す]
[変ホ長調と同じなので]♭3つ
- 嬰イ短調
答え [表示]答え [隠す]
[嬰ハ長調と同じなので]♯7つ
- 嬰ト短調
答え [表示]答え [隠す]
[ロ長調と同じなので]♯5つ
- ニ短調
答え [表示]答え [隠す]
[ヘ長調と同じなので]♭1つ
- 次の調号の調は何短調ですか?
- ♯3つ
答え [表示]答え [隠す]
[イ長調の短3度下が主音なので]嬰ヘ短調
- ♭1つ
答え [表示]答え [隠す]
[ヘ長調の短3度下が主音なので]ニ短調
- ♯6つ
答え [表示]答え [隠す]
[嬰ヘ長調の短3度下が主音なので]嬰ニ短調
- ♭5つ
答え [表示]答え [隠す]
[変ニ長調の短3度下が主音なので]変ロ短調
- 次の調の調号を書きましょう。
- es-moll
答え [表示]答え [隠す] - gis-moll
答え [表示]答え [隠す]
検索
© 2008-2020 by Takuya Shigeta